名字伝言板(掲示板)
「名字伝言板」とは名字由来netのユーザーの皆さまが名字や家紋等に関連することについて自由に情報をやり取りする伝言板(SNS)です。
※多くの利用者のご迷惑となるような不適切な書き込みを発見された方は「通報」ボタンをご利用ください。
※投稿内容に旧字や異体字などが含まれる場合、投稿自体失敗してしまう場合もございます。 また、差別につながる用語など自動で弾かれる場合もございますので、御理解の上ご利用ください。
※不適切な書き込み・興味本位の書き込みは、多くの利用者のご迷惑となりますので、不適切な書き込みが無いようご協力をよろしくお願いいたします。上記に反する書き込みにつきましては、削除させていただくこともありますのでご了承くださいませ。
この伝言板は57855人が見ています
| 名字について情報がほしいです |
|---|
|
【限定地域】なし(全国OK)
かつて実在した苗字
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/02/11 23:40:14
|
|
今は実在が確認できないが過去には実在が確認されていた苗字を紹介しています。

|
コメント一覧
No. 156
【126】「藺阿弥〜いあみ」
現京都府京都市で室町時代に畳師が、い草(藺草)の「藺」に時宗の阿弥号の「阿弥」を合体させて、できたとされる苗字。
後に「伊阿弥〜いあみ」に改姓した可能性あり。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/28 21:56:13
【126】「藺阿弥〜いあみ」
現京都府京都市で室町時代に畳師が、い草(藺草)の「藺」に時宗の阿弥号の「阿弥」を合体させて、できたとされる苗字。
後に「伊阿弥〜いあみ」に改姓した可能性あり。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/28 21:56:13

No. 155
【125】「砂子瀬〜すなこせ」
弘前藩(現青森県弘前市が藩庁)の藩士にいたとされるが、この藩士が明治新姓時に「砂瀬」に改姓したため、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/28 21:51:32
【125】「砂子瀬〜すなこせ」
弘前藩(現青森県弘前市が藩庁)の藩士にいたとされるが、この藩士が明治新姓時に「砂瀬」に改姓したため、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/28 21:51:32

No. 152
【124】「中櫨〜なかはじ」
江戸時代の木地師にいたとされる苗字。
のちに「羽実〜はじつ」姓に改姓したため、なくなったとされる。
ちなみに「木地師」とは、轆轤を用いて椀や盆などの木工品を加工、製造する職人のことである。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/24 23:46:24
【124】「中櫨〜なかはじ」
江戸時代の木地師にいたとされる苗字。
のちに「羽実〜はじつ」姓に改姓したため、なくなったとされる。
ちなみに「木地師」とは、轆轤を用いて椀や盆などの木工品を加工、製造する職人のことである。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/24 23:46:24

No. 150
【123】「金売〜かねうり」
平安時代の武将である源義経の従者にこの苗字の人がいた。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/24 23:41:05
【123】「金売〜かねうり」
平安時代の武将である源義経の従者にこの苗字の人がいた。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/24 23:41:05

No. 149
【122】「根来呂〜ねごろ」
1781年から1789年の間に現和歌山県和歌山市から現香川県三豊市に移住した際に「和歌〜わか」姓に改姓したため、なくなったとされる苗字。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/24 23:38:35
【122】「根来呂〜ねごろ」
1781年から1789年の間に現和歌山県和歌山市から現香川県三豊市に移住した際に「和歌〜わか」姓に改姓したため、なくなったとされる苗字。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/24 23:38:35

No. 148
【121】「一法寺〜いっぽうじ?」
正しい読み方不明。
戦国時代に現大分県から現福岡県福岡市に来た際にはこの表記であったとされる。
現存が確認できないため、もしかしたら「一坊寺〜いちぼうじ、いっぽうじ」に表記を変更した可能性あり。
ちなみに由来は、鎌倉時代の武士である大友直久の幼名の「一法師丸〜いっぽうしまる」から。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 22:02:52
【121】「一法寺〜いっぽうじ?」
正しい読み方不明。
戦国時代に現大分県から現福岡県福岡市に来た際にはこの表記であったとされる。
現存が確認できないため、もしかしたら「一坊寺〜いちぼうじ、いっぽうじ」に表記を変更した可能性あり。
ちなみに由来は、鎌倉時代の武士である大友直久の幼名の「一法師丸〜いっぽうしまる」から。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 22:02:52

No. 147
【120】「藤別当〜とうべっとう」
江戸時代に現鳥取県西伯郡大山町にあったとされる苗字。
のちに「当別当〜とうべっとう」と表記を変更したためなくなった思われる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:56:54
【120】「藤別当〜とうべっとう」
江戸時代に現鳥取県西伯郡大山町にあったとされる苗字。
のちに「当別当〜とうべっとう」と表記を変更したためなくなった思われる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:56:54

No. 146
【119】「体〜?」
読み方不明。
奄美群島の一文字姓にあったとされる。
1953年の日本復帰時に「岡」を追加して「体岡〜たいおか」に改姓したため、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:54:22
【119】「体〜?」
読み方不明。
奄美群島の一文字姓にあったとされる。
1953年の日本復帰時に「岡」を追加して「体岡〜たいおか」に改姓したため、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:54:22

No. 145
【118】「九十茂田〜つくもだ」
江戸時代に米沢藩(現山形県米沢市が藩庁)の藩庁にいたとされる。
のちに「九十九田〜つくもだ」と表記を変更したためなくなったと思われる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:52:29
【118】「九十茂田〜つくもだ」
江戸時代に米沢藩(現山形県米沢市が藩庁)の藩庁にいたとされる。
のちに「九十九田〜つくもだ」と表記を変更したためなくなったと思われる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:52:29

No. 144
【117】「打始〜うちはじまり」
奈良県御所市で明治新姓時にこの姓を申請したところ、「打集〜うちあつめ」と誤記したことでなくなったとされる苗字。
由来は家の前の山道を広げるために杭打ちを始めたことから。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:50:20
【117】「打始〜うちはじまり」
奈良県御所市で明治新姓時にこの姓を申請したところ、「打集〜うちあつめ」と誤記したことでなくなったとされる苗字。
由来は家の前の山道を広げるために杭打ちを始めたことから。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:50:20

No. 143
【116】「六谷田〜ろくやた」
江戸時代に前橋藩(現群馬県前橋市が藩庁)と伊勢崎藩(現群馬県伊勢崎市が藩庁)の藩士にいたとされる。
のちに「六弥太〜ろくやた」と表記を変更した可能性あり。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:47:39
【116】「六谷田〜ろくやた」
江戸時代に前橋藩(現群馬県前橋市が藩庁)と伊勢崎藩(現群馬県伊勢崎市が藩庁)の藩士にいたとされる。
のちに「六弥太〜ろくやた」と表記を変更した可能性あり。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/22 21:47:39

No. 142
【115】「名無師〜なむし」
四国八十八箇所の巡礼者が命名したことが始まりである。
江戸時代に現高知県安芸郡で「菜虫〜なむし」に改姓し、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/21 05:20:19
【115】「名無師〜なむし」
四国八十八箇所の巡礼者が命名したことが始まりである。
江戸時代に現高知県安芸郡で「菜虫〜なむし」に改姓し、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/21 05:20:19

No. 141
【114】「敷部〜しきぶ」
豊後大友氏の配下にこの苗字の人がいる。
文安頃の文書に「敷部 彈正忠」と書いてあり、筑後の士(さむらい)であろうか?
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/12 22:15:05
【114】「敷部〜しきぶ」
豊後大友氏の配下にこの苗字の人がいる。
文安頃の文書に「敷部 彈正忠」と書いてあり、筑後の士(さむらい)であろうか?
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/12 22:15:05

No. 140
【113】「次枝〜つぐえだ?」
正しい読み方不明。
江戸時代末期に現三重県伊勢市の伊勢神宮に伊勢参りをしに行ったところ、神主からこの苗字を賜ったとされる。
現存確認できないため、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/12 22:06:17
【113】「次枝〜つぐえだ?」
正しい読み方不明。
江戸時代末期に現三重県伊勢市の伊勢神宮に伊勢参りをしに行ったところ、神主からこの苗字を賜ったとされる。
現存確認できないため、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/12 22:06:17

No. 139
【112】「萬司重〜ますしげ」
江戸時代に長州藩(現山口県萩市が藩庁)の福原氏から賜ったとされる苗字で、明治新姓時に「増重〜ますしげ」に表記を変えたことでなくなったとされる苗字。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/12 22:03:18
【112】「萬司重〜ますしげ」
江戸時代に長州藩(現山口県萩市が藩庁)の福原氏から賜ったとされる苗字で、明治新姓時に「増重〜ますしげ」に表記を変えたことでなくなったとされる苗字。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/12 22:03:18

No. 138
【111】「深歳〜ふかとし?」
正しい読み方不明。
宮崎県東諸県郡国富町深年から発祥した苗字で、江戸時代にこの表記でいたとされる。
のちに「深年」と表記を変えた可能性あり。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/12 21:58:19
【111】「深歳〜ふかとし?」
正しい読み方不明。
宮崎県東諸県郡国富町深年から発祥した苗字で、江戸時代にこの表記でいたとされる。
のちに「深年」と表記を変えた可能性あり。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/12 21:58:19

No. 137
【110】「長射〜ながい?」
正しい読み方不明。
江戸時代に現熊本県玉名郡長洲で年貢を一番納めたことで称したのがはじまり。
のちに「中逸〜なかいつ」に改姓したため、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/11 19:18:26
【110】「長射〜ながい?」
正しい読み方不明。
江戸時代に現熊本県玉名郡長洲で年貢を一番納めたことで称したのがはじまり。
のちに「中逸〜なかいつ」に改姓したため、なくなったとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/11 19:18:26

No. 136
【109】「賤谷〜しずのめ、しずや?」
正しい読み方不明。
熊本県上天草市大矢野町の小字の賤の女から発祥した苗字。
のちに「静谷」と表記を変えた可能性あり。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/11 19:14:55
【109】「賤谷〜しずのめ、しずや?」
正しい読み方不明。
熊本県上天草市大矢野町の小字の賤の女から発祥した苗字。
のちに「静谷」と表記を変えた可能性あり。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/11 19:14:55

No. 135
【108】「高野木〜こうのぎ」
南北朝時代に南朝方に高野木氏がいた。
新潟県長岡市に高龍神社があり、この神社は高野木氏が龍神の住む土地に居住したことからできたとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/11 19:12:26
【108】「高野木〜こうのぎ」
南北朝時代に南朝方に高野木氏がいた。
新潟県長岡市に高龍神社があり、この神社は高野木氏が龍神の住む土地に居住したことからできたとされる。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/11 19:12:26

No. 134
【107】「葛濱〜くずはま」
武蔵国北埼玉郡葛濱発祥の苗字。
秀郷流藤原姓である。
佐野松田系図に「下河邊行方の子 行平を葛濱四郎」
中興系図に「葛濱、藤、木國下野、大河戸下総守行方男四郎行平、称之」
東鑑巻44に「葛濱左衛門尉」
とある。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/07 21:16:21
【107】「葛濱〜くずはま」
武蔵国北埼玉郡葛濱発祥の苗字。
秀郷流藤原姓である。
佐野松田系図に「下河邊行方の子 行平を葛濱四郎」
中興系図に「葛濱、藤、木國下野、大河戸下総守行方男四郎行平、称之」
東鑑巻44に「葛濱左衛門尉」
とある。
投稿者:つーさん 投稿日時:2019/04/07 21:16:21

| コメント投稿 |
|---|
「名字伝言板」に書きこむには、ログインが必要です。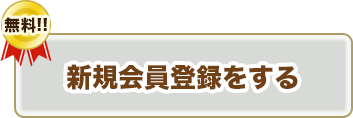
|

 「連濁(れんだく)」について
「連濁(れんだく)」について

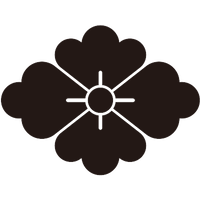 花菱
花菱

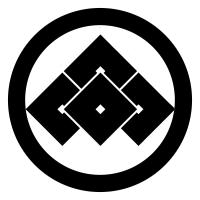









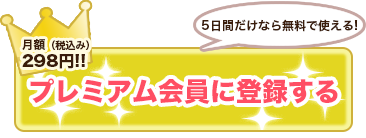
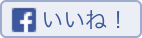


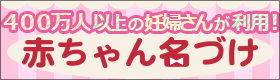
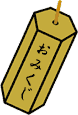

 全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
珍しい名字について語りまし…
 全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
名字について情報がほしいで…
 全国/
その他
全国/
その他
